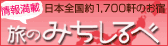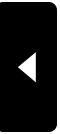2009年07月10日
祇園祭 神輿洗い
祇園祭も始まり10日が経ちました。
鉾町の山・鉾建てもはじまり、お祭ムードも高まっています。
昼間はお迎え提灯の行列もありました。
八坂神社でも神輿が本殿前に鎮座して、披露されています。

今日は夕刻より、八坂神社の神事である神輿洗いがありました。
神輿を鴨川で清める行事で、威勢のいいお兄さんが八坂神社で神輿を担いでいました。


17日の神幸祭で、神輿に乗った御神体が、お旅所(神様の主張所)に鎮座します。
24日の還幸祭は、御旅所を出た神輿が氏子の町を練り歩き、神社へ帰ります。
“後の祭り”とも呼ばれ、こちらのほうが盛大です。
皆さんは祇園祭りを、鉾の巡行だと思っていませんか?
鉾の巡行は、祇園祭が始まった所以の、疫病退散の宮参りの行列が
盛大になったものと考えられており、町衆がお祭を楽しむための行事であります。
対して、神輿の行事は八坂神社の神事として行われるものです。
祇園祭行事
7月1日 - 吉符入(きっぷいり)。祭りの始まり。
7月2日 - くじ取り式。下記参照。
7月7日 - 綾傘鉾稚児社参。
7月10日 - お迎え提灯。
7月10日 - 神輿洗い。
7月10日から13日まで -山建て鉾建て。分解収納されていた山・鉾を組み上げ、懸装を施す。
7月13日 - 長刀鉾稚児社参(午前)。
7月13日 - 久世駒形稚児社参(午後)。
7月14日 - 宵々々山。
7月15日 - 宵々山。
7月16日 - 宵山。14~16日をまとめて「宵山」と総称することもある。
7月16日 - 宵宮神賑奉納神事。
7月17日 - 山鉾巡行。
7月17日 - 神幸祭(神輿渡御)。
7月24日 - 花傘巡行。元々、この日に行われてた後祭の代わりに始められたもの。
7月24日 - 還幸祭(神輿渡御)。
7月28日 - 神輿洗い。
7月31日 - 疫神社夏越祭(えきじんじゃなごしまつり)。祭りの終わり。
Wikipediaより http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD
@せいじ
鉾町の山・鉾建てもはじまり、お祭ムードも高まっています。
昼間はお迎え提灯の行列もありました。
八坂神社でも神輿が本殿前に鎮座して、披露されています。

今日は夕刻より、八坂神社の神事である神輿洗いがありました。
神輿を鴨川で清める行事で、威勢のいいお兄さんが八坂神社で神輿を担いでいました。


17日の神幸祭で、神輿に乗った御神体が、お旅所(神様の主張所)に鎮座します。
24日の還幸祭は、御旅所を出た神輿が氏子の町を練り歩き、神社へ帰ります。
“後の祭り”とも呼ばれ、こちらのほうが盛大です。
皆さんは祇園祭りを、鉾の巡行だと思っていませんか?
鉾の巡行は、祇園祭が始まった所以の、疫病退散の宮参りの行列が
盛大になったものと考えられており、町衆がお祭を楽しむための行事であります。
対して、神輿の行事は八坂神社の神事として行われるものです。
祇園祭行事
7月1日 - 吉符入(きっぷいり)。祭りの始まり。
7月2日 - くじ取り式。下記参照。
7月7日 - 綾傘鉾稚児社参。
7月10日 - お迎え提灯。
7月10日 - 神輿洗い。
7月10日から13日まで -山建て鉾建て。分解収納されていた山・鉾を組み上げ、懸装を施す。
7月13日 - 長刀鉾稚児社参(午前)。
7月13日 - 久世駒形稚児社参(午後)。
7月14日 - 宵々々山。
7月15日 - 宵々山。
7月16日 - 宵山。14~16日をまとめて「宵山」と総称することもある。
7月16日 - 宵宮神賑奉納神事。
7月17日 - 山鉾巡行。
7月17日 - 神幸祭(神輿渡御)。
7月24日 - 花傘巡行。元々、この日に行われてた後祭の代わりに始められたもの。
7月24日 - 還幸祭(神輿渡御)。
7月28日 - 神輿洗い。
7月31日 - 疫神社夏越祭(えきじんじゃなごしまつり)。祭りの終わり。
Wikipediaより http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD
@せいじ
2009年07月10日
祇園祭:<お迎提灯巡行>
たまたま前を通ったので、携帯にて写真を撮ったのでちょっとボケてしまっていますが、これが終わる頃には四条大橋で神輿洗式が始まります。
「祇園祭」と言えば-宵山・山鉾巡行-ばかりが取り上げられますが、7月中を通じて色々な行事が行われていますので、その他の神事もチェックしてみてはいかがでしょうか?
2009年07月09日
祇園祭:<ちまき>
この、<ちまき>はその祇園祭で販売されるちまきです。
それぞれの山鉾の<ちまき>については、一般的には祇園祭の宵々々山(7月14日)頃からそれぞれの鉾町で販売されるもので、今は販売」されておりませんが、一足早く「菊水鉾」の関係者の方から頂きました。
(八坂神社の<ちまき>はすでに販売しているようです)
ありがとうございました。
京都の方はご存知ですが、<ちまき>と言っても中を開けても何も無く、食べられる<ちまき>ではありません。
これから、来年の祭までの一年間「無病息災」を願って各家庭の玄関口に飾られるお守りです。
(一昨年頃から、一部「黒主山」では生麩の入った食べられる<ちまき>を販売しているようですが・・)
この<ちまき>の「菊水鉾」は元治元年の「蛤御門の変」による大火で消失した幾つかの鉾の中にも含まれていて、長い間祇園祭に登場することはありませんでしたが、先に書きました関係者の方の先々代の社長が、鉾町にお世話になった感謝の意を込めて個人の私財を再建にあて、昭和27年頃に見事に再建され、また祇園祭にその雄姿を現すこととなったようです。
今では観光色が強くなってきましたが、元々は町衆の祭である「祇園祭」、ここにも町衆の力によって保たれたものがあったのですね・・。
元来京の都や日本全国に発生した疫病の退散を願って始まった「祇園祭」、今年の新型インフルエンザの退散を願って、皆さんの家の玄関口にも<ちまき>を飾ってはいかがでしょうか?
2009年07月03日
大舩鉾の宵山

嵐山の鵜飼を楽しんでいると、
コン♪チキチン~♪♪とお囃子の演奏が近づいてきました
赤い提灯には、大舩鉾の文字。
ん 大舩鉾
大舩鉾

祇園祭で登場する山鉾は全部で32基。
でも、大舩鉾はどこにも見あたりません・・・。
実はこの大舩鉾は、五百年余前、足利義教将軍の台命にて祇園祭が再興された応永29年(1422年)に建設されたといわれています。
しかし、その後応仁の乱、京都の大火、維新の騒乱・蛤御門の変にて、三度も類焼し犠牲となってしまいました
鉾の焼失以来、巡行には参加しないものの、町内の祭事が衰退することを惜しむ
四条町(新町通四条下ル)の若手有志がお囃子の復興
を提唱し、以前より交流の深かった同じ新町通の岩戸山囃子方の指導を受け、
平成9年の宵山において、およそ130年ぶりに大舩鉾のお囃子を復活させました!!!

現在では、30余名の囃子方(写真の方達 )がおられ、
)がおられ、
毎年宵山の期間中(7月13日~16日)には、かつて大舩鉾のあった四条町においてお囃子の演奏が行われます。
嵐山の鵜飼期間中でも、大舩鉾のお囃子を聴けるのは7月1日だけ
レアな演奏を聴きに、宵山には是非、四条町へ足を運んでみて下さい

 a*y*a
a*y*a
2009年07月01日
祇園祭りが始まりました
@せいじです
2009年05月15日
葵祭
葵祭を見にいきました
御苑だけでも約一万人ものお客さんが見にこられていて、驚きました。
行列中は、わかりやすい解説があり楽しく見ることができました。
 写真は牛車、風流傘、斎王代です
写真は牛車、風流傘、斎王代です




御苑だけでも約一万人ものお客さんが見にこられていて、驚きました。
行列中は、わかりやすい解説があり楽しく見ることができました。
 写真は牛車、風流傘、斎王代です
写真は牛車、風流傘、斎王代です



2009年05月14日
祭の前日・・明日は「葵祭」
明日は「葵祭」の日です。
京都の三大祭(葵祭・祇園祭・時代祭)の中でも最も歴史が深く
約1400年以上も前から続く由緒あるお祭です。
今年の「葵祭」のヒロイン『斎王代』には裏千家・千宗室家元のご長女
が選ばれて、明日のお祭で大役を勤められるようです。

これは御所の 建礼門前大通りにある観覧席の中ほどから「建礼門」
に向って撮った今朝の様子です。
この観覧席も多くの観覧者の方に埋め尽くされます。
京都の三大祭(葵祭・祇園祭・時代祭)の中でも最も歴史が深く
約1400年以上も前から続く由緒あるお祭です。
今年の「葵祭」のヒロイン『斎王代』には裏千家・千宗室家元のご長女
が選ばれて、明日のお祭で大役を勤められるようです。
これは御所の 建礼門前大通りにある観覧席の中ほどから「建礼門」
に向って撮った今朝の様子です。
この観覧席も多くの観覧者の方に埋め尽くされます。