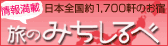2009年06月24日
囲碁 本因坊発祥の地
良く見ると真ん中の座面には碁盤の目が彫られており、それを挟むように椅子が両側に設置されています。
これは囲碁「本因坊」の発祥の地で、それを記したモニュメントとして今年の1月に設置されました。
寺町通りにあった寂光寺(現在は東山二王門西)の塔頭「本因坊」に住んでいた僧侶の日海は信長・秀吉の時代から囲碁の名人として名高く、徳川家の命を受けて、「本因坊算砂」と改名し、幕府の碁所を任されました。
算砂は、江戸に屋敷を拝領した後もこの「本因坊」を本居として、春に江戸入りをし、年末に京へ戻る暮らしをしていました。
以降「本因坊」の名前は世襲で受け継がれましたが二十一世の秀哉は、真の実力者が「本因坊」を名乗るべきとしてその名跡を日本棋院に譲り渡し、昭和二十一年に「本因坊戦」が誕生したとのことです。
今年の1月10日にこのモニュメントを設置された時にはプロ棋士の今井俊也九段と滝口政季九段がこの石製の碁盤で序盤の数手を打ち完成を祝ったそうです。
囲碁のお好きな方は碁石を持参すれば自由に対局が出来るそうなので、いかがでしょうか?